こんにちは、nocotoです。
先日ある企業の役員さんが、もうすぐ退職するけどいろいろな手続きが分からないということで、相談にのりました。
その時の話をシェアします。
ちなみに私は、サラリーマンだった夫が退職し、起業するまでの手続きをほぼ全て行った経験があります。
私自身も物販で稼げるようになり、どのような立場で行こうかと、勉強してきました。
個人の時代となってきたので、これから会社を起こしたり、フリーランスとなって働く方は増えて行くでしょう。
そんな方のお手伝いとなれば幸いです。
退職後に起業したい人へ向けた内容となっておりますが、無職となる方にとっても、途中までは参考になるかと思います。
退職直後にするべきこと
会社に所属している間は社会保険は給与天引きとなっていますが、退職したらご自身で支払いをしなければなりません。
手続き期間が短めなので、退職前から心積りしておくといいでしょう。
退職後から納める健康保険とは?
もしかしたら知らない人も多いかもしれませんが、会社員の健康保険料は、個人と会社が折半で納めています。
なので、たくさん納めている感覚はあったとしても、ご自身では半額しか納めていないという、大変お得な状態なのです。
もし会社を設立して、少なくとも会社員時代の給料と同じだけの報酬を得ようとすれば、あなたはこれまで納めていた健康保険料の2倍の額を、あなた自身が稼いで納めることになります。
これは後で話す厚生年金についても同じことです。
これを聞いただけで起業におじけづいてしまう人もいるかも!?
自信がない場合は思い切り報酬を下げるとか、個人事業主から始めるという方法もありますから。
起業して間もなくは、収入が安定しないことが多いです。
健康保険に関しては、個人事業主の場合、救済措置があります。
それが任意継続被保険者制度になります。
ややこしいので念を押しますが、会社を設立するのではなく、個人事業主になる場合の話です。
会社を設立する場合は、社会保険として、これまでの2倍をあなた自身が支払わなければなりません。
個人事業主の場合、任意継続被保険者制度を選ばなければ、国民健康保険に加入することになります。
保険料は、前年の1〜12月の所得、加入者数、年齢などによって変わりますので、各区役所や市町村役場で確認が必要になります。
これはホームページでシミュレーションができる地区もあるので探してみてください。
結構な金額にきっと驚かれると思います。
任意継続被保険者制度を選択した場合、会社での報酬をもとに、保険料を算出します。
こちらには早見表ですぐに金額を知ることができます。
多くの場合は任意継続の方がお得になると思いますが、個人の状況によっては逆の場合もありますので、両方の確認は必須です。
また、報酬を多くもらっていた人ほどお得感があります。
金額を算出する際に、報酬の上限が30万円と決められています。
東京都にお住まいで、会社での月の報酬が40万円だったと仮定すると、上限が30万円なので、保険料を算出する基準は30万円のところを見ます。
その場合、月の保険料が34,920円となります。
金額は住んでいる地域によって変わります。
早見表の折半額ではなく、全額をご自身で支払っていくことになります。
任意継続でも多く感じてしまうと思いますが…。
手続きは退職日の翌日から20日以内です!
過ぎてしまうと権利が無くなりますので、早めに手続きの準備をしておきましょう。
退職日を確認できる書類が必要で、それがない場合には会社からの証明を受けることが必要になります。
必要な書類はこちらに↓
健康保険に関しては以上になります。
できれば退職前に、国民健康保険と任意継続被保険者制度のどちらがお得になるか比べておきましょう。
厚生年金はどうなる?
会社員の時は、健康保険料と厚生年金保険料を、給料から天引きされ、会社が代理で納付しています。
退職すれば、自分で両方を納めることになります。
個人事業主または無職になる場合
国民年金は20歳から60歳までの40年間納めることとされています。
60歳未満で退職すれば、個人事業主になる場合、厚生年金に変わって国民年金を納めることになります。
令和3年4月~令和4年3月分の国民年金保険料は、16,610円(月額)です。
第2号被保険者から第1号被保険者に変わる手続きが必要となります。
| 手続き窓口 | 住所地の市区役所または町村役場 |
|---|---|
| 添付書類 | 年金手帳または基礎年金番号通知書 |
| 提出期限 | 退職日の翌日から14日以内 |
| 提出者 | ご本人または世帯主 |
日本年金機構のホームページからお借りしました。
退職証明書等、退職日の分かるものがあった方がいいと思います。
もし会社員である配偶者の扶養に入る場合は、配偶者の勤務している事業所を通じて手続きをし、第3号被保険者となります。
第3号被保険者は年金を納める必要がありません。
会社設立の場合
会社を設立する場合は、引き続き厚生年金を納めることになります。
厚生年金は国民年金と違い、会社員である以上、70歳までは納めなくてはなりません。
多くの人は65歳から老齢年金の受給開始になりますが、会社員を続けていれば、年金をもらいながら70歳までは厚生年金を納めるということになります。
月末に退職し、翌月からすぐに会社をスタートさせられる場合は、地域の年金事務所等で、健康保険と共に会社が変更になった旨の手続きをすることになります。
もし退職日が月末でない場合、例えば5月20日に退職し、翌月から新会社という場合は5月分の厚生年金を納めていないということになり、国民年金を一ヶ月分納める必要があります。
なるべく月末に退職するのがお得です。
しかし、もし新会社が5月21日~31日の間にスタートということであれば、国民年金を納める必要はありません。
以上、慣れない手続きは早めに準備しておきましょう。
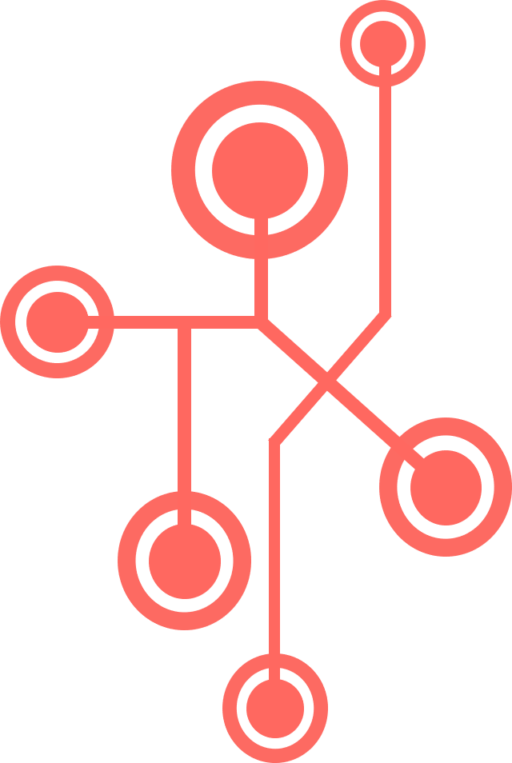 nocoto-style
nocoto-style

